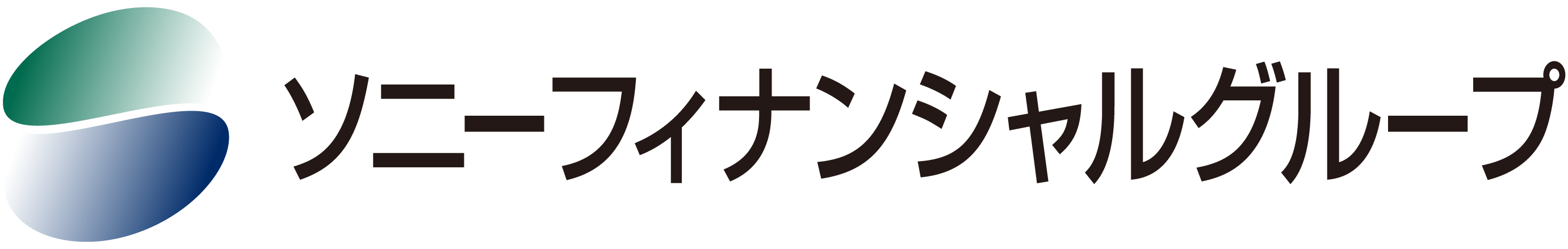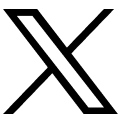資産寿命記事
節約=我慢ではない!家計管理の基本、ポイント10選
2025.09.02

ソニーフィナンシャルグループでは、個人の経済的な健全性を示す「資産寿命」を、自分らしい人生を実現するために欠かせない要素のひとつとしています。老後の生活に向けた資産形成など、将来にわたって必要な資産をどのように生み出し、備えるべきなのか。
本記事では、人生を豊かにする家計管理の基本となるポイントをお伝えします。
多くの方が、将来や老後について不安があり、お金は貯めておいた方がよいと感じています。とはいえ、財布の紐をギュッと締め、とにかく節約を重ねて質素な生活を送るのが、「お金を管理している」ことではありません。重要なのは、お金の流れを見やすくして、予算通りにお金を使っているのかどうかをチェックし、修正していくこと。お金の管理が上手にできれば、無駄遣いが減り、貯蓄が増え、必要なものを買えるようになります。決して「節約=我慢」をするのではなく、人生を豊かにするための家計管理。ここでは、そんな家計管理のポイントを10個紹介します。
はじめに…
お金を管理するうえで大切なことは「収支の把握」「予算を立てる」「具体的に管理する」です。まず、お金の出入りを見やすくして、何にどれくらい使っているのかわかりやすくします。そして、どれくらいお金を使うのか計画を立て、その通りに実行できているかチェックをします。この一連の流れが「お金を管理すること」となります。
基礎編
家計管理のポイント1:家計の「収支」を把握する
ファーストステップの「収支の把握」には、以下のポイントがあります。
- 支出の分類を理解する
- お金を管理する口座を分ける
- 家計簿をつける
一つずつ、解説していきます。
まずは、「支出の分類」を理解します。支出には大きく分けて「消費・投資・浪費」の3種類があります。
消費
消費は、生活に必要な支出です。住居費、食費、光熱費、水道費、交通費などがこれに当たります。必ず出ていくものなので固定支出とも呼ばれています。
投資
投資は、将来のための支出です。お金をふやすための株式の購入代金などの他に、資格取得のための参考書代やセミナー代など「自己投資」するお金も含まれます。
浪費
浪費は、平たく言えば無駄遣いです。たとえば、コンビニに行った際になんとなく買ったお菓子や雑誌代、不必要なブランド品の購入に費やしてしまったお金などです。
支出の分類を理解したら、次は「お金を管理する口座」を分けましょう。「管理する口座は少ない方がいい」と考え、ひとつの口座しか使っていない人もいるかもしれませんが、お金を管理するうえで重要なのは「お金の流れをしくみ化」すること。
準備する口座は以下の3つです。
収入用口座
会社からの給料など収入を入れる口座です。ここに入ってきたお金を、貯蓄用と支出用の口座へそれぞれ振り分けていきます。
貯蓄用口座
貯金用の口座です。貯蓄の目的がいくつかある場合には、複数作っておいてもよいでしょう。収入用の口座にお金が入ってきたらすぐに貯蓄用の口座に移します。
支出用口座
固定費や生活費など支出にあてるお金を入れる口座です。
そして、最後のポイントが「家計簿」をつけること。毎月のお金の流れを把握するために、やはり家計簿は有効です。毎日つけるのが面倒という人は、スマートフォンの家計簿アプリを使うのはいかがでしょうか。買い物レシートを読み込ませるだけで内容を自動で記録してくれるものがあります。また、前月との比較をグラフ化するなど、お金の流れを把握するのに便利な機能もあります。
また、クレジットカードの明細を家計簿代わりにするのもひとつの方法です。大きな買い物だけでなく日常の買い物でもクレジットカードを利用すれば、クレジットカードの明細が家計簿代わりになります。レシートを管理したり、家計簿をつけたりすることが難しければ、このように他の方法で管理すればいいのです。
家計管理のポイント2:予算を立てる
お金を上手に管理できる人は、目標をしっかりと立てられる人です。生活に必要なお金は「いくら」で、欲しいものを買うには「いつまでに」「いくら」貯めるのか計画を立てておきましょう。
理想的な支出の割合
消費:投資:浪費は、7:2:1の割合であることが理想的と言われています。生活に必要な部分にはきちんとお金を使い、将来の自分にも投資し、たまには息抜きやご褒美としてお金を使う。このバランスを意識しましょう。
目標と将来の支出(マイホーム・教育費・自己投資のための留学費用など)
いつまでにいくら貯めたいのか目標を立てましょう。その際は、「◯年後にマイホームの頭金として〇円を貯める」というように、期間と金額を具体的に設定します。
毎月の費目別予算を設定
将来の目標が決定したら、月々に使えるお金についても決めましょう。「食費」「日用品費」「交通費」「医療費」「交際費」などの費目別に、毎月の予算を設定します。これまで費目別予算を意識せずお金を使ってきた場合は、どの費目にいくら設定したらいいのかわかりにくいと思いますが、毎月続けていくうちに感覚がつかめてきて、使いすぎを防げるようになります。
家計管理のポイント3:お金を「目的別」に振り分ける
ここからは、お金を具体的に管理する方法について説明します。
ポイントは、銀行口座や封筒、財布などを利用して、お金を目的別に振り分けることです。
給料日に給料を振り分ける
収入用口座に入ってきたお給料は、あらかじめ立てた予算通りに支払い口座、貯蓄口座に振り分けましょう。お金を使ってしまう前に、振り分けることがポイントです。振り分けは給料日に行いましょう。
毎月お金を複数の口座に振り分けるのが面倒だったり、忘れてしまったりする人は、銀行の自動入金サービスを利用するとよいでしょう。
生活費は費目別の封筒(財布)に入れて管理する
支払口座と貯蓄口座へ振り分けられて残ったお金が当月の生活費です。生活費は予算に応じて費目別の封筒や財布を用意して振り分けましょう。月末に生活費が残っていれば、貯蓄用口座へ入金しましょう。
お金が貯まらない人ほど、小さなお金を軽く考える傾向があります。少額にこだわっていても意味がないと思っているのかもしれません。しかし、節約上手な人は、小さなお金であっても大切に考えます。このような意識や態度が、最終的には大きなお金につながります。
ここからは、少しの見直しで後々の大きなコストカットにつながる、カンタン節約方法についても紹介します。
家計管理のポイント4:保険の内容が自分やライフプランに合っているか検討する
固定支出から見直しを行うときは、まず保険の内容が自分やライフプランに合っているかを検討しましょう。必要な保険の内容は家族構成やライフプラン、資産の状況などによって変化するため、改めて見直してみると大きな節約につながることがあります。
家計管理のポイント5:毎月の住居費や通信費を見直す
基本的に住居費は給料の3割が適当だとされています。それ以上だと貯金までなかなかお金が回らなくなります。状況によっては、住まいの変更も検討しましょう。
また、今使っている携帯電話やインターネットのプランも見直しましょう。大手キャリアのスマートフォンを利用している人なら、格安SIMに変更することで、月々数千円の節約につながることもあります。
家計管理のポイント6:自家用車が本当に必要なのか検討する
車を持っているとガソリン代や駐車場代、自動車税や車検費用などの維持費、時には修理代までかかってしまいます。車を使う頻度が少ないのであれば、思い切って手放すことも節約には有効です。車を所有せずに、必要な場合だけカーシェアリングやレンタカーを利用することで、大きく支出を減らすことも期待できます。
結婚してからのお金の管理方法は、夫婦の間で役割分担を決めるなど、あらかじめルールを決めることが大切です。夫婦間でのお金の管理方法もいくつか紹介しますので、自分たちに合ったやり方をお試しください。
夫婦で管理編
今回は、結婚をしたばかりの若い夫婦(子どもなし)の例で考えてみます。
家計管理のポイント7:共同口座で一緒に管理する
夫婦の収入用口座を同一にし、共同管理するという方法です。この方法は共働き夫婦に多く見られます。双方が家計支出を把握できるメリットがありますが、反面お互いの残り収入や貯蓄状況が不明になりやすいというデメリットもあります。「月末に黒字が出たら貯蓄用口座に入金する」などルールを明確にしておくことがこの方法を続けていくコツです。
家計管理のポイント8:どちらかが一括管理する「お小遣い制」を導入する
妻か夫のどちらかが収入を一括管理し、自由に使えるお金を互いにお小遣いとして分配する方法です。
特に、教育費や住宅ローンなど支出が重なる期間は、家庭に入ってくるお金と出て行くお金を一元管理できるというメリットがあり、「臨時出費があった場合はどうするか」「飲み会の多い時期はどうするか」など、定期的な見直しや柔軟に相談しあうことがこの方法を続けていくコツです。
家計管理のポイント9:費目別に役割分担する
「夫が食費と光熱費を担当」、「妻が家賃と交通費を担当」、など、費目別に夫婦で役割分担する方法です。自分がどこまで払えばよいのかが明確になっている点はメリットですが、どちらか一方に負担が片寄ると不満が生じてしまいます。金額差が大きくなってしまった場合の調整方法をあらかじめ定めておき、定期的にルールを見直すようにしましょう。
家計管理のポイント10:貯蓄管理と支出管理で役割分担する
先ほどの費目別ではなく、貯蓄管理と支出管理で役割分担する方法です。たとえば夫が生活費を妻に渡し(妻が支出管理)、残りのお金を自分で管理(夫が貯蓄管理)します。収入額に差がある夫婦に多く見られる方法ですが、妻からは夫の貯蓄額が見えづらく「自分ばっかり好きなことにお金を使って」と不満が募ることもあります。
とはいえ、お金を管理することばかりに注力しすぎてしまうと、気持ちも窮屈になってしまいます。最後に、うまくストレスも発散させながら、お金を管理するためのコツを紹介します。
番外編
ストレスを溜めない家計管理
「お金を管理する=節約する」と捉えがちですが、そうではありません。必要な物、必要な場合にはお金を迷わず使いましょう。たとえば、自分の成長や将来につながる、モチベーションの向上につながるため使うのは必要なお金です。使うべきところには使い、使うべきではないところには使わない、メリハリをつけてお金を使うことが大事です。
また、ストレス解消のためのお金を事前に予算へ組み込むことも方法の一つ。度を越した浪費はNGですが、自分へのご褒美ゼロというのは、精神的に無理が生じます。そこで、ストレス解消につながる出費は、あらかじめ予算に組み込むようにしましょう。自分にとってのストレス解消法は何か?そのために毎月いくら使うべきか?を考え、毎月の費目に加えます。
家計を見直し、使うべきところは使って豊かな人生を
「お金を管理する方法」などと聞くと、なんだか難しそうに感じられるかもしれません。また、いかにも我慢を強いられるようで、窮屈に感じてしまう人もいるでしょう。
でも、今回紹介したコツは今日からでもすぐに実践できるものばかり。また、我慢という感覚ではなく、家計を見直すことで、「もっと楽しいことにお金を使えるようになる」と考えてみるのはいかがでしょうか?そうすれば、より豊かな人生をおくれるはずです。